天野 博/法学部闘争委員長
『支配に抗う〈正史〉』:序文
闘いはすでに一年半に及ぼうとしている。この記録の刊行を企ててから一年、昨年10月出版の準備に入り、発刊を約束してからも半年以上がたつ。やる気を失ってしまい、 そのまま放ったらかしにされていた。その原稿を整理し、この時期に、あえて活字にしようとしたのは、もちろん、理由――立命闘争の新しい担い手の登場――のあるところだ。



しかし、我々が、未だ公けにされていない重大な資料とともに、この闘争の記録を、闘う学友の共同の財産としなければならない理由はいくつかあるとしても、出さない理由は、たった一つしかない。この記録が、危うく手に入れた資料の一つ一つに価値づけられるとしても、より高く、我々の闘いの激しい道程のドキュメントに意義をおこうとするなら、そのわけは、熱気のさめたキャンパスに”あいまいな自伝によりかかる”ような記録をおくりたくはないからだ。
冬の夜のかがり火に、我々が、はっきりと見た果てない青春の行程を、あいまいにしてはなるまい。記録は、過去を”思い出”のうちに語るようにしてしまうふやけた時間の位相の危険から「経過」を純化させる。
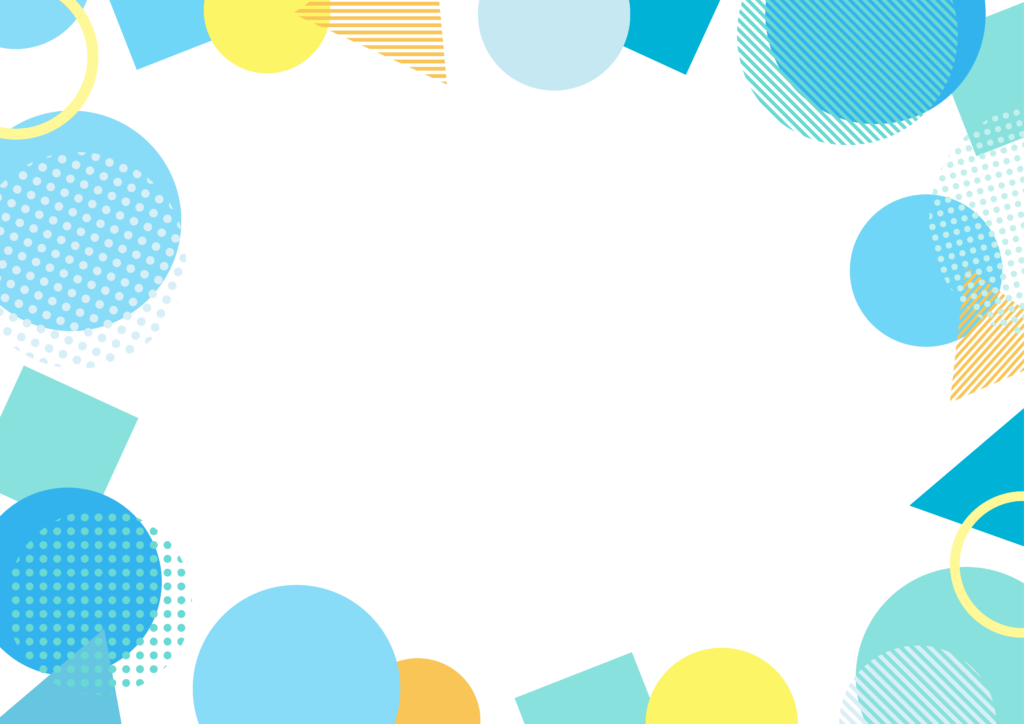
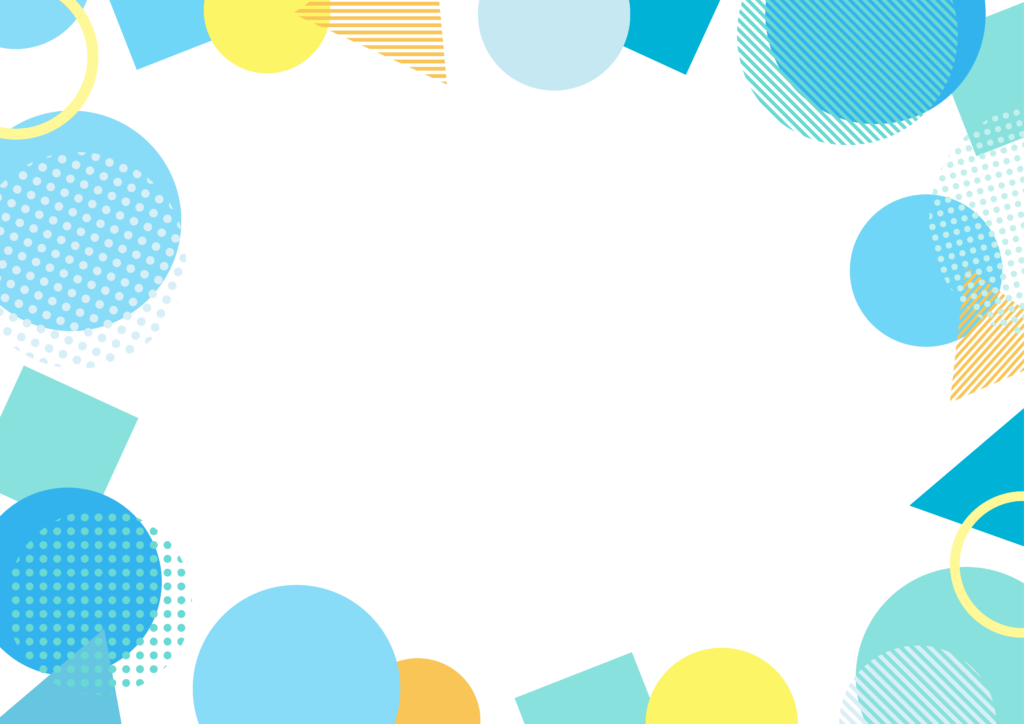
この反省――記録の行間から発した我々の問いはかつて、千の人々のありかを照らしだした千の炎のゆくえであり、問いつめたいのは、かげろう――陽炎への変貌だ。
この記録の第一の意義を、どんなありふれた圧制者も、いつもきまってやる歴史の捏造、歪曲に抗する〈正史〉を世に問うことにおく。身分制議会(旧立命館民主主義)の全能の独者による統治(ボナパルティズム)への変質ーケレンスキーからスターリンへの変身を刻明に書きしるし、身をもちくずすばかりの立命館大学を野辺おくりすることだ。
次ぎに、明らかになる解放されるべき対象――打倒する対象と主体とを緊しめる、総括の提起、行動のうむことば(実践思想)をつくりえたか、という自問を提起することだ。
支配者の知りえない遠くにまで行くことを決意した我々は、何に対して闘い、今、どこまできているのであろうか。記録は、その視座と座標軸をさし示すことになろう。

語られる68年、69年学園闘争の全国的な昂揚が、いかに巨大な風波をつくりえたとしても、それが一般論である限りにおいて、我々の闘いの固有の様々な局面と縁のないものにならざるをえない。その一方で、一般的な全国的な情況は、そしてそれをつきだす国家権力は、我々の想いを阻害し、闘いの成熟を待ちはしなかった。
今、これらの過去、我々の総括を、一つの昇りつめる曲線に交わる“円環”への主張に低めることなく完了しなければならぬ。 代々木・民青に対して、ふだんに身がまえることをよぎなくされた、いびつな〈全共闘〉は、突発的、不連続に闘かってきた。明確な総括や内省もない、自分の実践への評価も放棄したまま、さらなる実践へかりたてられてきた〈全共闘〉の真実の記録は、なお〈全共闘〉の地平にいる人々への自己の不断の蘇生――自己変革――根本からの総括への重要なきっかけとなろう。
5月20日、何らなす術もない無力感――自己嫌悪・自己喪失からの爆発的行動は、我々の深い下意識――倒錯した世界意識の怒りが、我々の闘いのはじめからおわりまで占めていた位置へのさめた反省を求めている。

くりかえされてきた総括しきれない行動は、ついに〈全共闘〉の死をもたらした。六月のひとりの女子学生の死は、〈全共闘〉の青春をして、時代を転換するエネルギーの未成をよくあらわしており、〈全共闘〉の死の跳躍と同義である。わだつみ像倒壊は〈全共闘〉の孤独の名分をしるしつづけることになろう。〈全共闘〉は、わだつみを肯定的に、しかしきっぱりと否定する。武藤理事会 は、わだつみを否定的に肯定する。
苦悩とともに「実践できる思想という意味ではなく、実践を表出している思想としての実践思想」がおしだされねばならない。
最も切実な、それ故に美しい思想が、しばしばくだらない姿をとることをよく納得し、闘いを継続せよ。
中国文化革命は、政治主義的情况志向派と反政治主義的情念派との垣根をとりはらった。(津村喬)
ねごとの多い昼寝からさめよ、佐藤がいそぐように、我々もまたいそがねばならない。 「造反にあとさきなし」(毛沢東)
最後の学部争委員会から、11番目の闘争主体――全学評議会運 動への連帯のことばを。
街頭ゲバは、どんなにエスカレートしても市民主義的示威の枠をこえない。学園闘争こそが、永続性・攻撃性・根底性ある内容の現実化として権力を脅かしたのだ。全共闘は、全国全共闘連合というわけのわからないものとなって(党派連合)、権力には、ゲバルト以外恐れるものではなくなった。
全共闘の限界を党派になりきれぬところの未熟さとしてしめくくってはならない。依然として問題は、自己の立っている基盤、その背景で、己を問う作業にある。闘争の真実化は、自分の内部に どうしても表現せずにはいられない確執をもつことにある。自分の中で対立するものがあるとき、闘争は内在するゆえに中断しない。そのとき、運動は、誰を通じてでも、どこにでもあらわれることができる。
67年10月8日にはじまり69年5月20日におわる長い闘いの深い意味は、単に”暴力”の登場にあっただけではなく、闘うベトナム人民を前にして拍手をおくるしか能のない苦痛――羞恥のこころ――原罪意識の復権にこそあった。山崎君は、日本人の心をつき動かし、じっとしておかせず、日大・東大闘争は、他諸階層のよってたつ基盤を問い、波及し普遍化した。
キャンパスのうすい意識、あいまいな現実に、鮮明な過去――出来事――思想を対置すること。思想としての記録。個別性と全体性の生きている関連の全く新しい段階、全共闘以後を理解しえないような党派には口ぶえを吹いてやればよい。
蒲田の自警団と立命の自警団とに共通する悲劇は無知である。ファシズムは、自警団――私的暴力の公然化にはぐくまれる。無知にはぐくまれる。自警団に、この〈正史〉をおくる意味はあるだろう。 いくつかのかくされてきた真相とともに。無知な自警団のファナティシズムには手を焼かざるをえないが、彼らのうしろにたつ資本家どもが、ほんとうの敵だ。
このさい、問題なのは、何もしない、もめ事がおこれば、難をさけるようにする現状追認――無気力集団の存在であろう。彼らこそ、〈全共闘〉を非力にし、武藤理事会の安寧をささえているのだ。
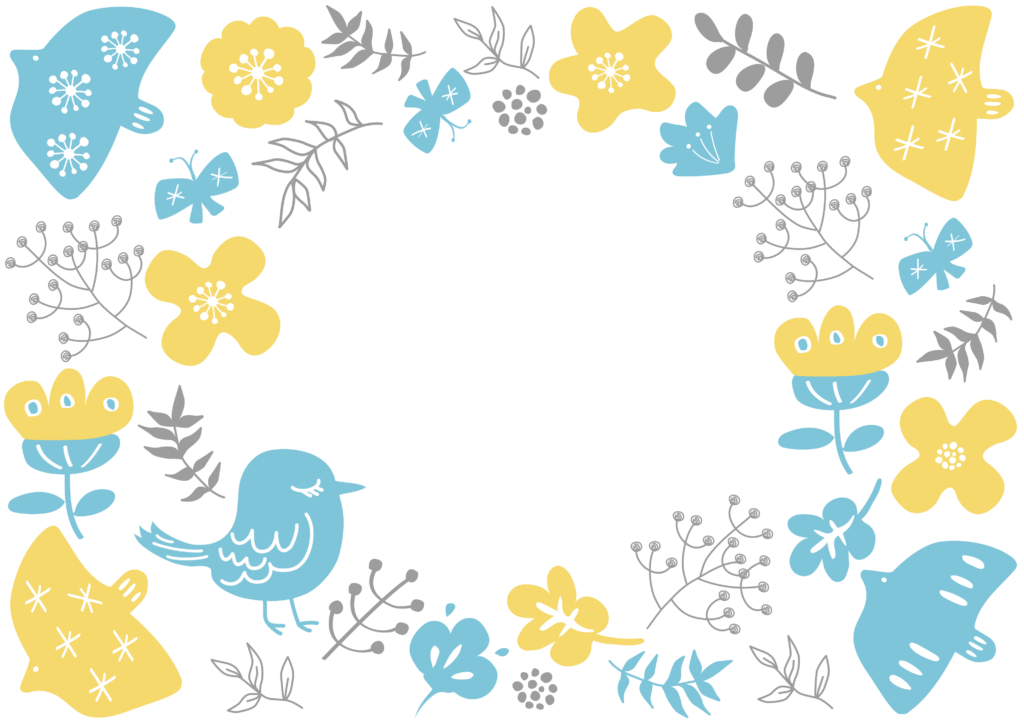
では、なぜ、代々木は「独裁」し、武藤総長は「退去命令」を乱発しなればならないのか。
そうだ、〈全共闘〉の存在が、危機的な支配の形態を強いているのだ。文句を言う人間が、みんな〈全共闘〉にみえてくる支配者の心理につつまれている御都合主義者武藤氏も、本当のことを言えば、平和や民主主義をことば通り実行したいのだ。〈全共闘〉にも集会・結社・出版の自由をみとめ、つじつまをあわせたい。〈全共闘〉への妄想におそわれている代々木や武藤理事会の、諸君を不快にさせる「独裁」と「専制」も、諸君こそが〈全共闘〉の全構造的な抑圧者であることを理解するまでつづこう。
彼らとともに、〈全共闘〉は学生でなく、寮連合下の寮生もまた 学生でないという発想は、頭蓋骨の暗い所にある理事者どもの〈差別の意識〉から出て、歴史のある局面熱狂する排外ナショナリズムの場で重大な役割をはたすにちがいない。代々木や武藤氏には、帝国主義者にならないという歯止めは、何ひとつない。

キャンバスの学友諸君! 〈全共闘〉は、無念にも「立命解放」と いう旗印をおろさなければならない。
この記録と総括(次篇)の刊行は、葬ったはずの過去の権力の現在の権力への延命を断たんとする刃となろう。立命館民主主義の体制化を批判しえた唯一の主体、大学が変わりうるという可能性を切り拓いたはずの無二の変革主体たる全共闘は、家父長(武藤理事会) と親族(キャンパスの学友諸君)に認知されない私生児のようだ。 貧しく傷ついた子は、あるいは幸せな家庭を築いているかもしれない父親にすてられ、失意のうちにある母親に会うことをもとめ、旅をつづけている。
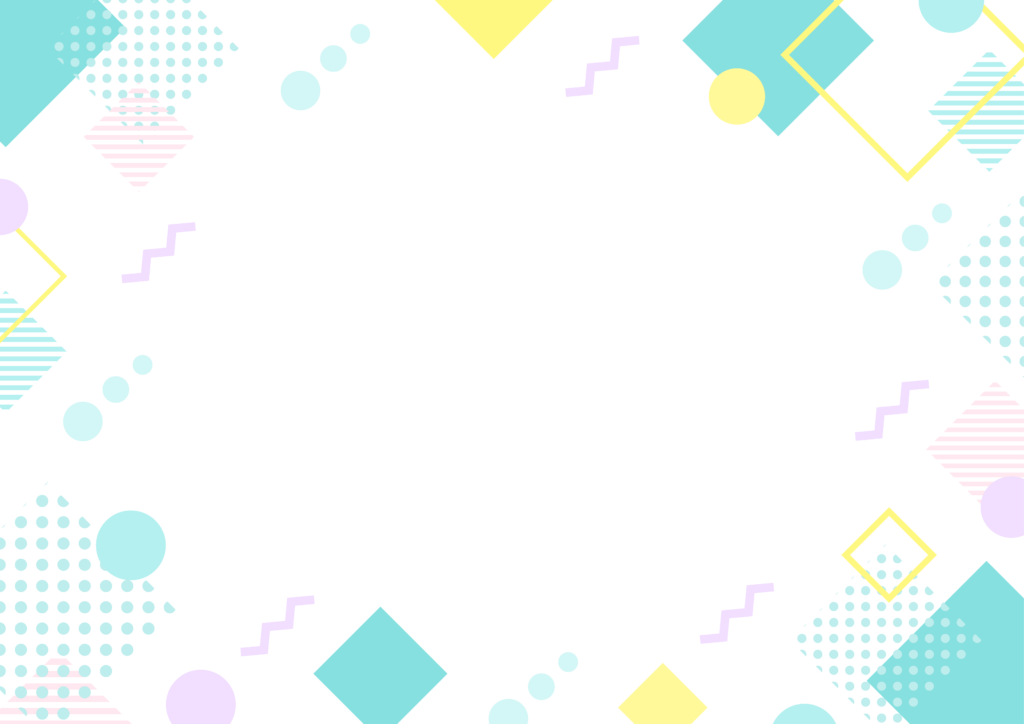
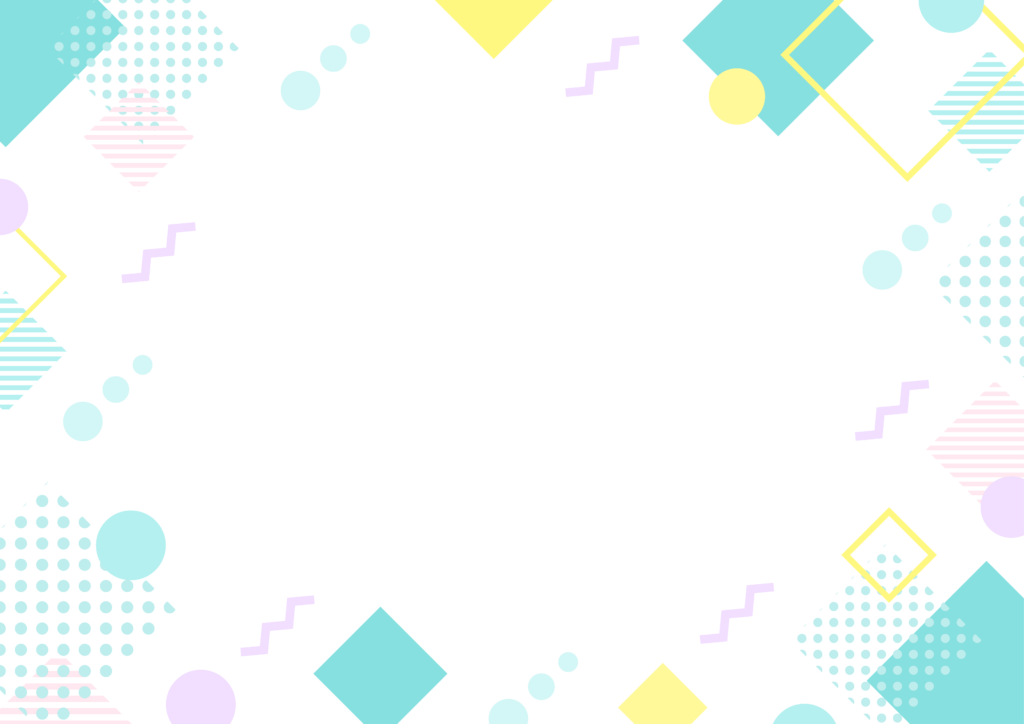
自分が、この世の中で果たしている役割を知ることはつらいことである。しかし、人は えらびもなく、試行誤のくやしさもないような人生をおくってはならない。 法学部闘争委会は、全共闘のいのちあるかたみの一切を継承し、人間と真理への冒涜者、代 々木、武藤理事会を諫め、正義を発動させる闘いに決起することを言明する。永い亡命を終え、全ての学友との相互変革の過程へ入る可能性を現実化することを提起し、法学部闘争委員会は、この記録が、自警団を打倒し、被害者とスネ者の館を爆破する新たな闘いの場の昂揚とともに、広く問われることを熱望している。
6月安保闘争の前進を目の当たりにして。
法学部闘争委員長 天野 博

コンテスタシオン!(立命館大全共闘機関紙より)
連絡先:tugobua1969@gmail.com
天野博(Amano Hiroshi)
